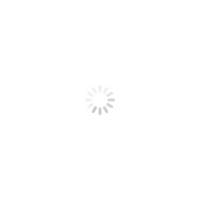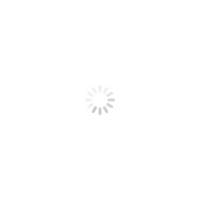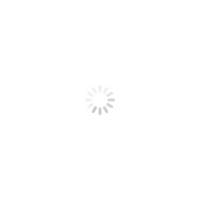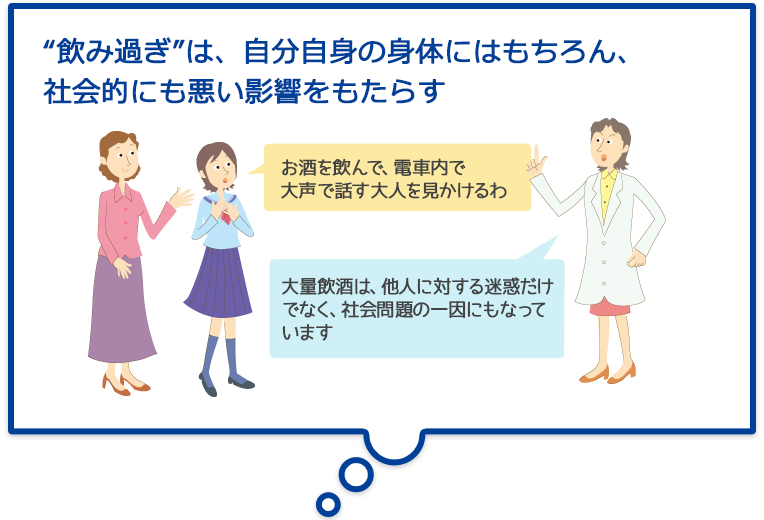
大量飲酒が及ぼす、家族や社会への悪影響
家族への影響
子どもを安全かつ安定した環境で育てることができなくなり、AC(アダルトチルドレン)※1、DV(ドメスティック・バイオレンス)※2、児童虐待などの問題を起こしやすい。また、会社を休んだり、飲酒運転事故を起こした際の賠償金などにより、経済的にも家計を圧迫する。
※1 AC:アルコール依存症の問題など、機能不全家族の中で成長した人。
※2 DV:夫や元夫、婚約者、恋人など親密な関係にある人からの暴力。
周囲の人への影響
飲酒運転事故を起こすことにより、相手にケガを負わせたり、命を奪ってしまう。周囲の人に対して、暴力をふるったり、暴言を吐いたりする。泥酔状態になると、公共の場の風紀を乱すことにもなる。
さらに、アルコール依存症となってしまうと、人間関係のトラブルなどに発展するケースが多くなります。
大量飲酒は、生活習慣病の原因にもなる
日本では、生活習慣病の増加が社会問題となっており、死亡する人の2/3近くがこれを原因としています。 その中で、糖尿病や高脂質異常、高血圧の危険因子といわれているものの一つが「大量飲酒」です。厚生労働省では、2000年~2012年「健康日本21」・2013年~2024年「健康日本21(第二次)」とこれまでも取組みを進めてきましたが、さらにアップデートし、2024年から2035年までの取組みとして「健康日本21(第三次)」を推進することとしています。そのうち、飲酒対策として以下の目標を掲げています。
- ○一日平均純アルコールで男性は40g、女性は20g(20g=ビール中びん約1本)を超えて多量に飲酒をしている割合を男女計10%以下に削減する(2032年まで)
※2022年時点で、男性13.5%、女性9.0% - ○20歳未満の飲酒をなくす(2032年まで)
「健康日本21(第三次)」の基本方針